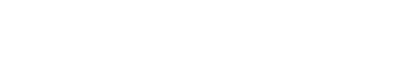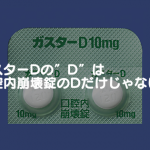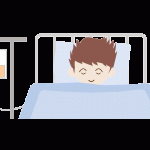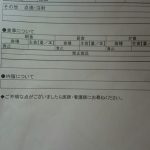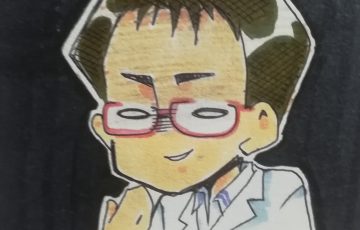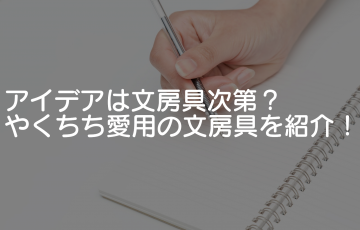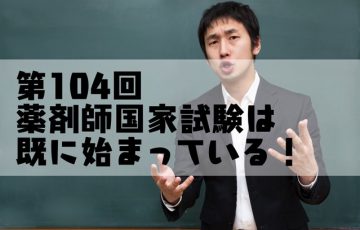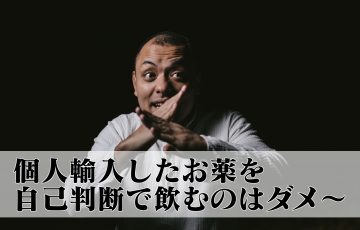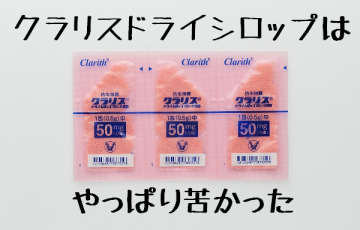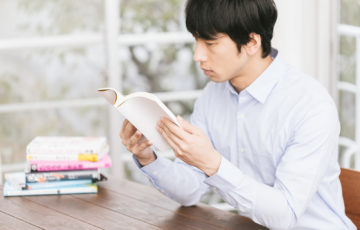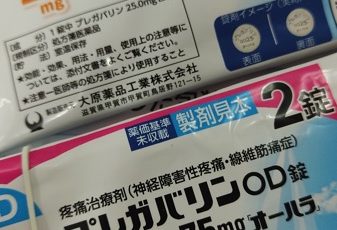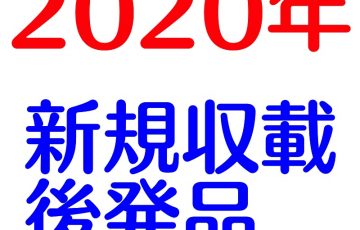高齢者と薬は切っても切れない関係にあります。
理由として・・・
- 高齢者は病気を複数抱えることで、複数の医療機関を受診するケースが多い
- 医師は患者が服用する全薬剤を把握せず、自分が受け持った領域(病気)だけを診て処方しがち(同じような薬が出ていることがある)
- 高齢者は腎機能など内蔵機能が衰えているので、薬の代謝能力が低下している
ただでさえ、代謝能力の衰えている高齢者が薬を多く処方・服用すれば、その副作用は出やすくなります。
日本老年医学会では、2015年11月に「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015」をまとめました。
この中で、特に慎重な投与が必要なものとして、抗精神病薬や睡眠薬、鎮痛薬など20領域の代表的な薬剤が載っています。
起こりやすい副作用だけでなく、「漫然と長期投与せず、減量、中止を検討する」や「可能な限り使用を控える」といったように、対策も付記しています。
栃木医療センターでは、医師と薬剤師が取り組む専門外来「ポリファーマシー外来」を開設し
多剤併用している患者さんの薬を確認し、それぞれの要否を判断し整理しています。
また、調剤薬局でも2016年4月から、かかりつけ薬剤師制度がスタートし
患者さんの氏名で薬局薬剤師が薬を一括で把握・管理しています。

薬剤師に処方権はないので最終的には医師の判断・責任にはなるのですが、
実際にお薬手帳を見ていても、薬が多いな、と感じる人は多いです。
1人の医師でも8種類とか処方しているケースもあります。
必要だから出しているのだろうから薬局から提案するにしても、しっかりと情報を収集して
的確に提案しないといけませんね。